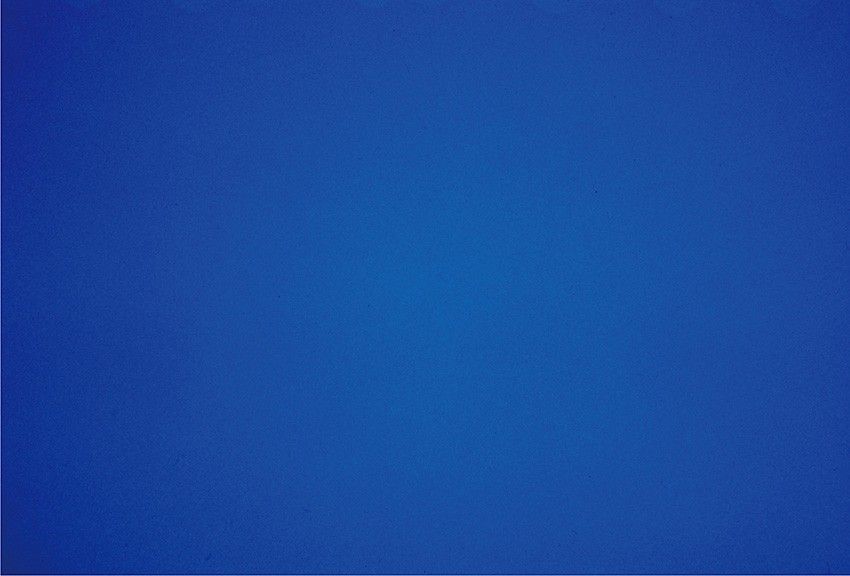『ブルームービー』©︎United Archives/Getty Images
映画の歴史において、青の映画、すなわちブルーフィルムという言葉には色彩とは別の意味合いがある。
かつては古いポルノ映画、とりわけ非合法で流通し、好事家の間でこっそりと上映される猥褻な映画のことをブルーフィルム、あるいはブルームービーと呼んだ。
ブルーフィルムの歴史は映画の歴史と同じくらい長いが、文字どおり青い映像を作ったのはポップアートの第一人者アンディ・ウォーホルだった。
ウォーホルは、アート表現の一環としてセックスを扱った実験映画
『ブルームービー』(1969年)を発表しているのだが、フィルムの特性を知らないままフィルターなしで撮影したため、フィルム一本まるごと青みがかった画になってしまった。
ウォーホルは意気消沈したが気を取り直して、猥雑と色みのダブルミーニングで「ブルームービー」と名付けたという逸話がある。
とはいえ、今、映画とブルーの組み合わせでポルノを連想する人はほとんどいない。’70年代こそ『青い体験』(’73年)、『青い経験』(’75年)といったイタリア産のお色気映画がヒットしたが、この「青」は日本の映画会社が“青春/性春”のイメージから勝手につけたもので、原題との関連はない。

『汚れた血』©︎Collection Christophel/AFLO
’80年代に育った筆者の世代であれば、フランスで“恐るべき子供”と呼ばれた3人の新鋭監督、レオス・カラックス、ジャン=ジャック・ベネックス、リュック・ベッソンが、それぞれに
『汚れた血』(’86年)、
『ベティ・ブルー』(’86年)、
『グラン・ブルー』(’88年)などで青の色調を前面に押し出した。

『ベティ・ブルー』©︎Everett Collection/AFLO
映画に“青の時代”があったとすれば、’80年代のフランスを想起するのは筆者だけではないだろう。
思えばどの作品にも生と死の狭間を漂うような感覚があり、映画の世界において、光と闇、白と黒との間はグレーではなくブルーではないのかという気にさせてくれる。

『グラン・ブルー』©︎Collection Christophel/AFLO
日本から世界に向けて、青という色を効果的に発信した映画監督といえば北野武をおいてほかにいない。北野武の映画もまた死のイメージがつきまとうものが多く、その寂寥とした詩情に青みがかったがよく似合う。
『HANA-BI』(’97年)をはじめ、北野作品のアート性をいち早く評価した海外の映画人や評論家は、青を基調とするひとつの美意識として「キタノブルー」と呼ぶようになった。

『HANA-BI』©︎Capital Pictures/amanaimages
また、映画の世界で極めつきの“青い映画”は、その名もズバリのデレク・ジャーマン監督作
『ブルー』(’93年)だろう。ジャーマンは’94年にAIDSの合併症で亡くなっており、『ブルー』の制作時には既に視力さえもほとんど失っていた。
ジャーマンは映画の全編が真っ青という前代未聞の映画を作り、死を前にしたジャーマン自身による朗読やサイモン・フィッシャー・ターナーの音楽を重ねて詩のような映画を生み出した。
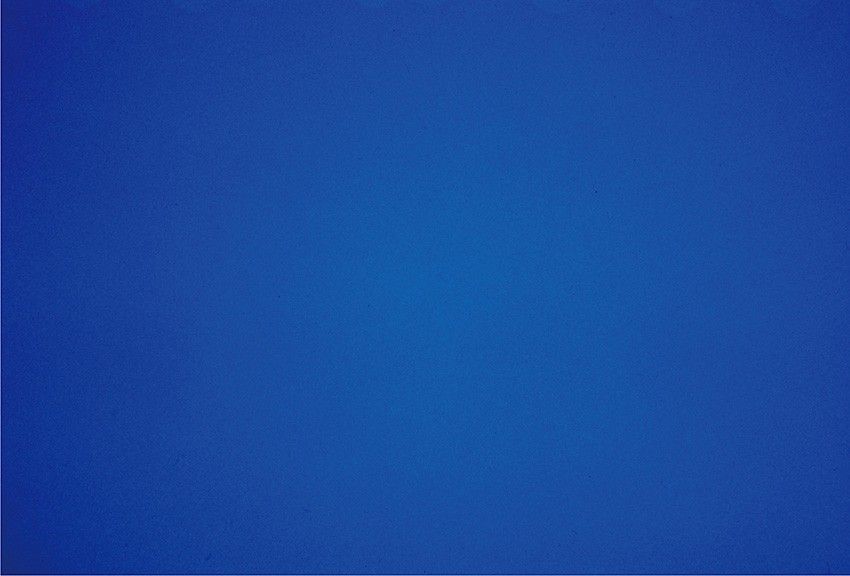
『ブルー』©︎Mary Evans/amanaimages
と、映画における青をかなり寂しいものとして書いてしまったが、2021年公開の?田恵輔監督のボクシング映画『BLUE/ブルー』の青は、挑戦者側が立つ青コーナーを意味している。
試合で勝ったことがない万年挑戦者の葛藤に優しい視線を注いだ名作であり、映画の“青”に新たな彩りを加えてくれたと思っている。